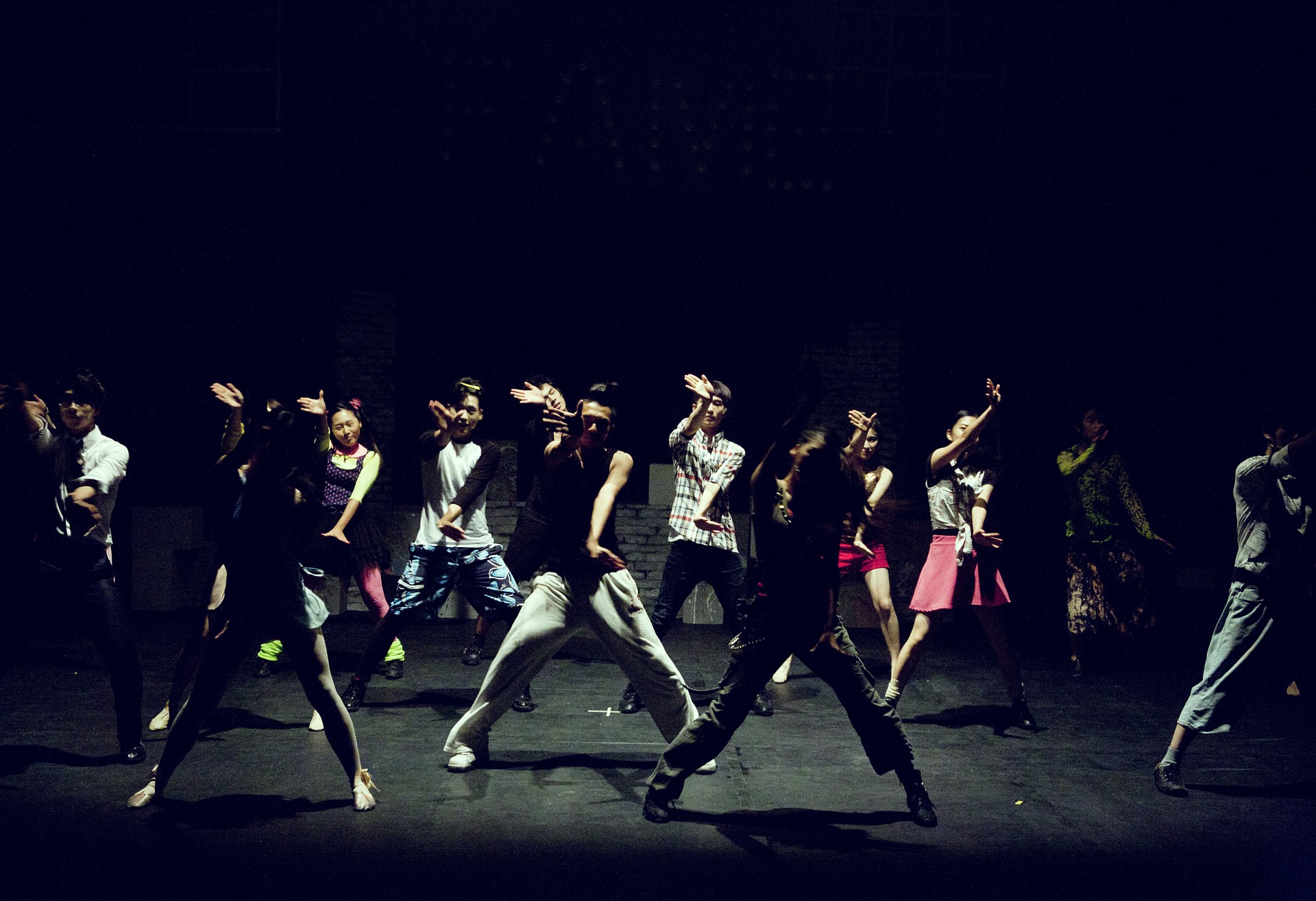茶番の語源は「茶番狂言」。
その言葉が省略されて、茶番といわれるようになりました。
目次
茶番の語源である「茶番狂言」とは何か?
茶番(ちゃばん)の語源となった
茶番狂言(ちゃばんきょうげん)とは
江戸時代の後期に流行った寸劇です。
江戸を中心に素人が役者のように演技をする劇で
茶番狂言の特徴は、最後に滑稽な落ちをつけること。
これは豆知識ですが、茶番狂言で落ちをつけるときは、その落ちに関連する物をお客さんにみせて、それを無料を配っていたそうです。
そのためお客さんは寸劇だけではなく、その無料配布されるものを目当てにする人も増えたとのこと。
茶番の語源の由来
「茶番狂言」をする演者はみな
本物の役者ではなく素人だったこともあり
「茶番狂言=ばかばかしい物事」
というイメージが定着したそうです。
その「茶番狂言」の狂言が省略されて
みえすいたばかばかしいことを
「茶番」というようになったのが由来です。
なぜ「茶番狂言」という名の劇なのか?【茶番狂言の由来】
そもそもなぜ
「茶番狂言」という名の劇なのか?
そこを読み解くと
「茶番」という言葉の
本当の由来がわかります。
「茶番」とは、劇場の楽屋で、
お茶の準備などをする役のこと。
この茶番を担当することになった人が
茶菓子などを落ちとして使った余興が
素人に広まり誕生した狂言が「茶番狂言」。
そのため「茶番」という言葉が
寸劇の名に使用されているそうです。
※江戸時代の人の日常生活が書かれた
当時の資料「俗耳鼓吹(ぞくじこすい)」にも
この「茶番」の存在が書かれています。
あわせて読みたい


江戸時代 (1603年から1868年まで)とは?どんな時代だった?【重要人物の死因も公開】
江戸時代とは?どんな時代だった? かの有名な「関ヶ原の戦い」が江戸時代の始まりのゴングといってもいいでしょう。 この戦いで徳川家康が勝利し1603年...
あわせて読みたい


厳選!日本語の語源や由来一覧【日常会話で使う言葉を中心にまとめました】
日常会話で使う日本語を中心に、語源や由来を一覧でまとめました! https://tromolo.jp/a https://tromolo.jp/ka https://tromolo.jp/sa https://tromolo.jp/ta ...