「下戸(げこ)」と「上戸(じょうご)」。
それらの言葉の語源や由来を辿ると
なんと飛鳥時代までさかのぼります。
あわせて読みたい

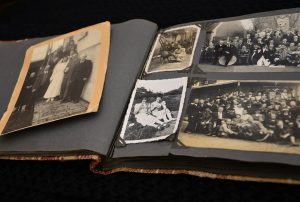
飛鳥時代 (592年から710年まで) とは?どんな時代だった?【日本の歴史をわかりやすく簡単に】
聖徳太子は、法隆寺を建てた人物。 日本人であれば誰もが知っている 日本に大きな影響を与えた偉人です。 聖徳太子が生きた時代は 今から約1400年も昔の...
飛鳥時代の後半(701年)から続く
日本の法律(律令制)の中の言葉で
「上戸」と「中戸」と「下戸」がありました。
あわせて読みたい


大宝律令とは何か?内容や制定理由は?【わかりやすく簡単な言葉で解説】
大宝律令(たいほうりつりょう)は飛鳥時代に制定された日本の律令です。 日本史上初めて、律と令がそろって 成立した本格的な律令とされています。 大宝律令とは...
「戸」とは、郷(ごう)における課税の
最小単位として使用されていた言葉です。
この「戸」は、人の数や資産によって
「上戸」と「中戸」と「下戸」に分かれ
貧しい人たちは「下戸」に分類されました。
貧しい「下戸」はお酒を買う余裕がなく
裕福な「上戸」はお酒をたくさん買える。
そういったイメージが由来となり
- 「お酒が飲めない人=下戸」
- 「お酒を飲める人=上戸」
というようになったとされています。
そう表現するようになった時期は
はっきりとはわかっていませんが
平安時代くらいだと考えられています。
あわせて読みたい


平安時代 (794年から1185年まで) とは?どんな時代だった?【重要人物の最期(死因)も公開中】
平安時代はどんな時代だったのか? この記事では平安時代の歴史について概要をわかりやすく簡単に解説して重要人物の最期も年表にまとめました。 平安時代とは?どんな...
豆知識ですが、日本の律令制は
唐(当時の中国)のシステムを参考に
藤原不比等らが作ったものです。
大宝律令などとよく呼ばれます。
この大宝律令は飛鳥時代後半である
701年に登場した日本の律令制です。
あわせて読みたい


藤原不比等ってどんな人?何をした人?【わかりやすく簡単な言葉で解説】
藤原不比等(ふじわらのふひと)は飛鳥時代から奈良時代初期までを生きた公卿です。 ※公卿(くぎょう):日本の役人の最高幹部 藤原不比等の誕生時期:659年 藤原不...
あわせて読みたい


大宝律令とは何か?内容や制定理由は?【わかりやすく簡単な言葉で解説】
大宝律令(たいほうりつりょう)は飛鳥時代に制定された日本の律令です。 日本史上初めて、律と令がそろって 成立した本格的な律令とされています。 大宝律令とは...
あわせて読みたい

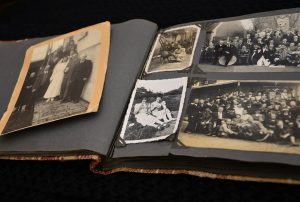
飛鳥時代 (592年から710年まで) とは?どんな時代だった?【日本の歴史をわかりやすく簡単に】
聖徳太子は、法隆寺を建てた人物。 日本人であれば誰もが知っている 日本に大きな影響を与えた偉人です。 聖徳太子が生きた時代は 今から約1400年も昔の...
あわせて読みたい


奈良時代 (710年から794年まで) とは?どんな時代だった?【日本の歴史をわかりやすく簡単に】
奈良時代とはどんな時代だったのか? この記事では奈良時代についてなるべくわかりやすく簡単に解説して出来事を年表や年号順にまとめました。 奈良時代...
あわせて読みたい


平安時代 (794年から1185年まで) とは?どんな時代だった?【重要人物の最期(死因)も公開中】
平安時代はどんな時代だったのか? この記事では平安時代の歴史について概要をわかりやすく簡単に解説して重要人物の最期も年表にまとめました。 平安時代とは?どんな...
あわせて読みたい


厳選!日本語の語源や由来一覧【日常会話で使う言葉を中心にまとめました】
日常会話で使う日本語を中心に、語源や由来を一覧でまとめました! https://tromolo.jp/a https://tromolo.jp/ka https://tromolo.jp/sa https://tromolo.jp/ta ...

