平安時代はどんな時代だったのか?
この記事では
平安時代の歴史について
概要をわかりやすく簡単に解説して
重要人物の最期も年表にまとめました。
目次
平安時代とは?どんな時代だった?

平安時代は、391年間(794年-1185年)続きました。
基本的に平安時代の期間は
桓武天皇が都を長岡京から
平安京へ移した年(794年)から
壇ノ浦の戦いで平氏が滅亡した年
(1185年)までの391年間を指します。
この平安時代では
藤原氏一族による
摂関政治がはじまります。
その後、上皇らによる院政が行われ、
平氏や源氏など武士の台頭へと続きます。
平安時代末期は、源平合戦とも呼ばれる
治承寿永の乱が始まり、平氏が滅亡。
源頼朝が鎌倉で幕府の政治を始め、
鎌倉時代へとつながっていきます。
あわせて読みたい


鎌倉時代 (1185年から1333年まで) とは?どんな時代だった?【日本の歴史をわかりやすく簡単に】
【注意】鎌倉時代の期間:1185年-1333年 最新の研究結果により鎌倉時代の始まりは1192年ではなく1185年からということがわかりました。※現在の教科書も変更されています...
この平安時代以降、
都の場所は明治時代までずっと変わりませんが
政治の中心地は時代ごとに変化していきます。
※江戸時代に幕府が江戸(東京)で開かれますが
都(みやこ)が京都から東京になる時期は明治時代。
あわせて読みたい


明治時代 (1868年から1912年まで) とは?どんな時代だった?【重要人物の死因も公開中】
明治時代とはどんな時代だったのか? この記事では明治時代の歴史について概要をわかりやすく簡単に解説して最初から最後までを年表にまとめました。 明...
平安時代の文化面においては、
菅原道真が遣唐使を廃止したことで
国風文化(こくふうぶんか)が栄えます。
十二単(じゅうにひとえ)や寝殿造、
枕草子や源氏物語なども
平安時代に完成したと言われています。
あわせて読みたい


清少納言の死因とは?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 清少納言の死因は不明です。 清少納言の誕生時期:966年 清少納言の死亡時期:1025年 ※清少納言の最期の年齢は約60歳 清少納言の最期の年齢は約60歳...
あわせて読みたい


紫式部の死因とは?暗殺された?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 紫式部の死因は不明です。 ※紫式部の最期の年齢は38歳 紫式部の誕生時期:978年 紫式部の死亡時期:1016年 紫式部は平安時代を生きた女性。 今から...
他にも、平仮名や片仮名などの
かな文字が広まった時代とも言われています。
※日本語の「カタカナ」の発明者:吉備真備
平安時代の最初から最後まで【重要人物の最期(死因)も公開】

794年(延暦13年)【平安時代】
797年(延暦16年)【平安時代】
802年(延暦21年)【平安時代】
- 坂上田村麻呂が胆沢城を築城
803年(延暦22年)【平安時代】
- 坂上田村麻呂が志波城を築城
804年(延暦23年)【平安時代】
805年(延暦24年)【平安時代】
806年(大同1年)【平安時代】
807年(大同2年)【平安時代】
- 伊予親王の変(冤罪で藤原吉子、伊予親王が死去)
809年(大同4年)【平安時代】
- 嵯峨天皇が即位(天皇期間:809年-823年)
810年(弘仁1年)【平安時代】
811年(弘仁2年)【平安時代】
- 坂上田村麻呂死去(享年53歳)
820年(弘仁11年)【平安時代】
- 弘仁格式の編纂(藤原冬嗣らが、弘仁格式を編纂)
822年(弘仁13年)【平安時代】
- 最澄死去(享年56歳)
※比叡山の中道院で亡くなる
あわせて読みたい


最澄の死因とは?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 最澄の死因は不明です。 最澄の誕生日:767年9月15日 最澄の命日:822年6月26日 ※最澄の最期の年齢は56歳 最澄が死ぬ前にいた最後の場所は 比叡山の...
824年(弘仁15年)【平安時代】
- 平城天皇死去(享年49歳)
835年(承和2年)【平安時代】
- 空海死去(享年62歳)
※空海の死亡は病気の可能性が高いが実際は不明
あわせて読みたい


空海の死因とは?どんな最後だった?生きている?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 空海の死因は不明です。 空海の誕生日:774年6月15日 空海の命日:835年4月22日 ※空海の最期の年齢は62歳 空海の死因として病死が濃厚ですが...
838年(承和5年)【平安時代】
- 遣唐使の派遣
※最後の遣唐使が派遣された年
842年(承和9年)【平安時代】
847年(承和14年)【平安時代】
- 円仁が帰国
850年(嘉祥3年)【平安時代】
- 仁明天皇死去(享年41歳)
- 文徳天皇の即位
857年(天安1年)【平安時代】
- 藤原良房が太政大臣に就任(皇族以外で初)
858年(天安2年)【平安時代】
- 文徳天皇死去(享年32歳)
- 清和天皇の即位(天皇期間:858年-876年)
- 円珍が帰国
- 藤原良房の摂政(皇族以外で初)
864年(貞観6年)【平安時代】
- 貞観大噴火(富士山が噴火した。富士山噴火史上最大と言われている。)
- 円仁(慈覚大師)死去(享年71歳)
※円仁(慈覚大師)の死因は熱病の可能性が高いが実際は不明
866年(貞観8年)【平安時代】
- 応天門の変(大納言の伴善男が応天門を放火)
※左大臣の源信にその罪を負わせよう計画するが結局バレてしまい、伴善男は流罪になる
869年(貞観11年)【平安時代】
- 貞観地震が発生
※陸奥で起きた大地震。多賀城が崩壊し、大津波によって1000名以上が亡くなった
872年(貞観14年)【平安時代】
- 藤原良房死去(享年68歳)
876年(貞観18年)【平安時代】
- 陽成天皇の即位(天皇期間:876年-884年)
※清和天皇が譲位し、陽成天皇が即位
880年以降【平安時代】
- 歌物語『伊勢物語』完成
- 日本最古の物語『竹取物語』完成
884年(元慶8年)【平安時代】
887年(仁和3年)【平安時代】
- 光孝天皇死去(享年57歳)
- 宇多天皇の即位(天皇期間:887年-897年)
888年(仁和4年)【平安時代】
891年(寛平3年)【平安時代】
- 藤原基経死去(享年55歳)
894年(寛平6年)【平安時代】
- 遣唐使の廃止
※菅原道真により遣唐使が廃止された
897年(寛平9年)【平安時代】
- 醍醐天皇の即位(天皇期間:897年-930年)
※宇多天皇が譲位し醍醐天皇が即位
901年(延喜1年)【平安時代】
902年(延喜2年)【平安時代】
- 延喜の荘園整理令(違法な土地所有を禁止)
903年(延喜3年)【平安時代】
- 菅原道真死去(享年57歳)
あわせて読みたい


菅原道真の死因とは?病気?暗殺?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 菅原道真の死因は不明です。 菅原道真の死因として 病死説などが一般的ですが 詳細は明らかになっていません。 菅原道真の誕生日:845年8月1日 菅原...
905年(延喜5年)【平安時代】
- 勅撰和歌集『古今和歌集』完成
※紀貫之らによって編集された
930年(延長8年)【平安時代】
- 醍醐天皇死去(享年50歳)
931年(承平1年)【平安時代】
- 宇多天皇死去(享年64歳)
935年(承平5年)【平安時代】
- 『土佐日記』完成
※歌人、紀貫之(きのつらゆき)が日記文学『土佐日記』を記した
939年(天慶2年)【平安時代】
941年(天慶4年)【平安時代】
- 藤原純友死去(享年48歳)
966年(康保3年)【平安時代】
969年(安和2年)【平安時代】
- 安和の変(藤原師尹が源高明を大宰府へ左遷した出来事)
- 円融天皇の即位
※冷泉天皇が譲位し円融天皇が即位 - 藤原実頼(さねより)が摂政に就任
- 高麗の使節が対馬を訪れる
970年(天禄1年)【平安時代】
- 藤原実頼死去(享年70歳)
- 藤原伊尹(これただ)が摂政に就任
972年(天禄3年)【平安時代】
- 藤原伊尹死去(享年48歳)
- 藤原兼通(かねみち)が関白に就任
975年(天延2年)【平安時代】
- 『蜻蛉日記(かげろうにっき)』完成
※蜻蛉日記は藤原道綱の母による日記
977年(貞元2年)【平安時代】
- 藤原兼通死去(享年52歳)
978年(天元元年)【平安時代】
- 紫式部誕生
990年(正暦1年)【平安時代】
- 藤原兼家(かねいえ)が関白に就任
- 藤原道隆(みちたか)が摂政、関白に就任
- 藤原兼家死去(享年61歳)
995年(長徳1年)【平安時代】
- 藤原道兼が関白に就任
- 藤原道兼死去(享年35歳)
996年(長徳2年)【平安時代】
- 『枕草子(まくらのそうし)』完成
※枕草子は藤原定子に仕えた清少納言による日本最古の随筆
998年(永年2年)【平安時代】
- 源頼義誕生
1008年(寛弘5年)【平安時代】
- 『源氏物語(げんじものがたり)』完成
※源氏物語は紫式部が書いた世界最古の恋愛小説
1016年(長和5年)【平安時代】
※紫式部は約40歳くらいの年齢で死去
あわせて読みたい


紫式部の死因とは?暗殺された?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 紫式部の死因は不明です。 ※紫式部の最期の年齢は38歳 紫式部の誕生時期:978年 紫式部の死亡時期:1016年 紫式部は平安時代を生きた女性。 今から...
1019年(寛仁3年)【平安時代】
1028年(万寿2年)【平安時代】
あわせて読みたい


清少納言の死因とは?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 清少納言の死因は不明です。 清少納言の誕生時期:966年 清少納言の死亡時期:1025年 ※清少納言の最期の年齢は約60歳 清少納言の最期の年齢は約60歳...
1028年(長元1年)【平安時代】
あわせて読みたい


藤原道長の死因は糖尿病ではない?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
藤原道長の死因は病死(糖尿病)だとされています。 しかし藤原道長が死亡した時代は 約1,000年も昔(平安時代)なので 実際の死因は明らかになっていません。 ※藤原道長...
1036年(長暦1年)【平安時代】
- 後朱雀天皇の即位
1040年(長久1年)【平安時代】
- 長久の荘園整理令
1045年(寛徳2年)【平安時代】
- 後朱雀天皇死去(享年35歳)
- 後冷泉天皇の即位
- 寛徳の荘園整理令
1051年(永承6年)【平安時代】
1052年(永承7年)【平安時代】
あわせて読みたい


平等院鳳凰堂とは?【歴史や見どころをわかりやすく解説】
平等院(びょうどういん)は 京都府宇治市にある寺院です。 平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)とは その中にある阿弥陀堂の別称で、 鳳凰が翼を広...
1063年(康平6年)【平安時代】
あわせて読みたい


鶴岡八幡宮とは?【歴史や見どころをわかりやすく簡単に解説】
鶴岡八幡宮(つるおかはちまんぐう)は 神奈川県鎌倉市にある神社です。 鶴岡八幡宮はどんな神社だったのか? 鶴岡八幡宮を建てた人は誰だったのか? &nb...
1068年(治暦4年)【平安時代】
- 後三条天皇の即位
1069年(延久1年)【平安時代】
- 延久の荘園整理令(記録荘園券契所を設置し荘園の所有者を審査)
例えば、石清水八幡宮領では、
34箇所の荘園のうち21か所は審査を通過し、
残りの13か所は審査で落ち権利が停止された。
この法令により
貴族や寺社の支配する荘園と
国司の支配する公領とが明確になった。
1072年(延久4年)【平安時代】
- 白河天皇の即位(天皇期間:1072年-1086年)
※後三条天皇が譲位し白河天皇が即位
1074年(延久6年)【平安時代】
- 藤原頼通死去(享年82歳)
1075年(承保2年)【平安時代】
- 源頼義死去(享年87歳)
1083年(永保3年)【平安時代】
- 後三年の役(~1087年)
※後三年の役とは、東北地方での清原家衡と源義家、清原清衡による争い(奥州藤原氏の誕生)
1086年(応徳3年)【平安時代】
- 堀河天皇の即位(天皇期間:1072年-1107年)
※白河天皇が譲位し堀川天皇が即位 - 白河上皇が院政を開始
1091年(寛治5年)【平安時代】
- 源義家への荘園寄進が禁止
1094年(寛治8年)【平安時代】
- 藤原伊房(これふさ)らが遼との私貿易で処罰
1095年(嘉保1年)【平安時代】
- 白河上皇が北面武士を設置
1096年(嘉保2年)【平安時代】
- 白河上皇が出家し白河法皇に
1105年(長治2年)【平安時代】
- 藤原清衡が中尊寺を建立
1107年(嘉承2年)【平安時代】
- 堀河天皇死去(享年28歳)
- 鳥羽天皇の即位
1108年(天仁1年)【平安時代】
- 源義親の乱
※源義家の子の源義親が九州で略奪を行い官吏を殺害(源義親は平正盛によって殺害)
1118年(永久6年)【平安時代】
- 平清盛誕生
1121年(保安2年)【平安時代】
- 藤原忠通(ただみち)が関白に就任
1123年(保安4年)【平安時代】
- 崇徳天皇の即位
※鳥羽天皇が譲位し崇徳天皇が即位 - 源義朝誕生
1124年(天治1年)【平安時代】
- 平泉中尊寺で金色堂が建立
1128年(大治3年)【平安時代】
- 奥州の藤原清衡死去(享年72歳)
1129年(大治4年)【平安時代】
- 白河法皇死去(享年77歳)
- 鳥羽上皇の院政が開始
1138年(保延4年)【平安時代】
- 北条時政誕生
1141年(永治1年)【平安時代】
- 近衛天皇の即位
※崇徳天皇が譲位し近衛天皇が即位
1154年(久寿1年)【平安時代】
1155年(久寿2年)【平安時代】
- 近衛天皇死去(享年16歳)
- 後白河天皇の即位(天皇期間:1155年-1158年)
1156年(保元1年)【平安時代】
1157年(保元2年)【平安時代】
- 巴御前誕生
※歴史に名を残した女侍
1158年(保元3年)【平安時代】
- 二条天皇の即位
※後白河天皇が譲位し二条天皇が即位 - 後白河天皇の院政が開始
1159年(平治1年)【平安時代】
1160年(平治2年)【平安時代】
- 源義朝死去(享年38歳)
あわせて読みたい

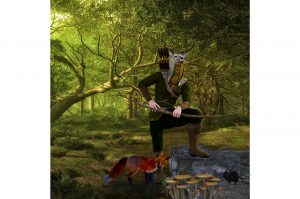
源義朝の死因とは?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 源義朝の死因は暗殺です。 ※入浴中に襲撃を受けて死亡 源義朝の誕生時期:1123年 源義朝の命日:1160年2月11日 ※源義朝の最後の年齢は37歳 ...
1164年(長寛1年)【平安時代】
1167年(仁安2年)【平安時代】
- 平清盛が太政大臣に就任
※武士で初めての太政大臣 - 日宋貿易が盛んになる
1170年(嘉応2年)【平安時代】
- 源為朝死去(享年31歳)
あわせて読みたい


弓術の達人「源為朝」ってどんな人?何をした人?【わかりやすく簡単な言葉で解説】
源為朝(みなもとのためとも)は 平安時代末期を生きた武将です。 誕生時期:1139年 死亡時期:1170年4月23日 https://tromolo.jp/heian 自らを鎮西八郎...
1173年(承安3年)【平安時代】
- 親鸞聖人誕生
1175年(安元1年)【平安時代】
- 法然が専修念仏を説き浄土宗を伝える
1177年(治承1年)【平安時代】
1179年(治承3年)【平安時代】
- 治承三年の政変(平清盛によって後白河法皇が幽閉)
1180年(治承4年)【平安時代】
- 治承寿永の乱が開始
- 以仁王や源頼政らが挙兵
- 以仁王死去(享年30歳)
- 石橋山の戦い
- 富士川の戦い
※富士川の戦いとは、源頼朝と平清盛の戦い(平清盛が敗走) - 源頼朝が侍所を設置
- 平清盛が後白河法皇の幽閉を解く
1181年(治承5年/養和1年)【平安時代】
- 養和の飢饉
- 後白河法皇の院政が再開
- 平清盛死去(享年64歳)
あわせて読みたい


平清盛の死因とは?どんな最後だった?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 平清盛の死因は病死です。 平清盛の誕生日:1118年2月10日 平清盛の命日:1181年2月4日 ※平清盛の最期の年齢は64歳 平清盛は最期、熱病にうなされな...
1183年(治承7年/寿永2年)【平安時代】
1184年(治承8年/寿永3年)【平安時代】
1185年(文治1年/寿永4年)【平安時代】
あわせて読みたい


壇ノ浦の戦いとは?決戦の場所はどこ?【簡単にわかりやすく解説】
壇ノ浦の戦い(だんのうらのたたかい)とは 平安時代末期に行われた歴史的な戦いです。 ※壇ノ浦の戦いの時期:1185年の春頃 https://tromolo.jp/heian こ...
1189年(文治5年)【平安時代】
あわせて読みたい


奥州合戦と何か?【わかりやすく簡単な言葉で解説】
奥州合戦(おうしゅうかっせん)は 平安時代末期に起きた戦いです。 https://tromolo.jp/heian 1180年から始まった 治承・寿永の乱の最後の戦争です。 https://tro...
最後に

この記事では
平安時代の歴史を
わかりやすく簡単に解説して
重要人物の最期(死因)などもまとめました。
少しでも参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


紫式部の死因とは?暗殺された?【生涯(最初から最期まで)もわかりやすく簡単に解説】
結論からいいますと 紫式部の死因は不明です。 ※紫式部の最期の年齢は38歳 紫式部の誕生時期:978年 紫式部の死亡時期:1016年 紫式部は平安時代を生きた女性。 今から...
あわせて読みたい


鎌倉時代 (1185年から1333年まで) とは?どんな時代だった?【日本の歴史をわかりやすく簡単に】
【注意】鎌倉時代の期間:1185年-1333年 最新の研究結果により鎌倉時代の始まりは1192年ではなく1185年からということがわかりました。※現在の教科書も変更されています...

