「四六時中」の語源や由来は何?
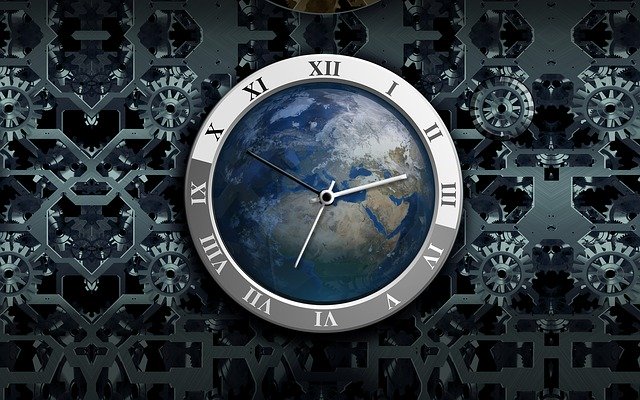
四六時中って「ずっと」とか「24時間中」って意味だよね?ん?あれ?なんで四と六なの??
 柴犬
柴犬
「四六時中」の語源や由来は何?
 柴犬
柴犬
「四六時中」の意味:一日中、24時間中
「四六時中」の語源や由来について
「四六時中」の語源や由来については
江戸時代の「二六時中」が起源となります。
※「二六時中」の意味:一日中
そもそも、なぜ24時間中が
「四六時中」といわれるのか?
この結論を簡単にまとめると
4(四)×6(六)が24になるからです。
「四六時中」の語源や由来となった
江戸時代の「二六時中」については
2(二)×6(六)で12になってしまいますが
それは、当時では昼と夜を6ずつに分け
1日を12時間で表していたからとなります。
(6×2=12)
参考文献:暮らしのことば 新 語源辞典
いまでは当たり前のように
一日は24時間で表しますが
それは明治時代からなのです。
作家である坂口安吾の作品の中で
「二六時中」という言葉が登場します。
ちなみに、太宰治の作品の中では
「四六時中」という言葉がでてきます。










